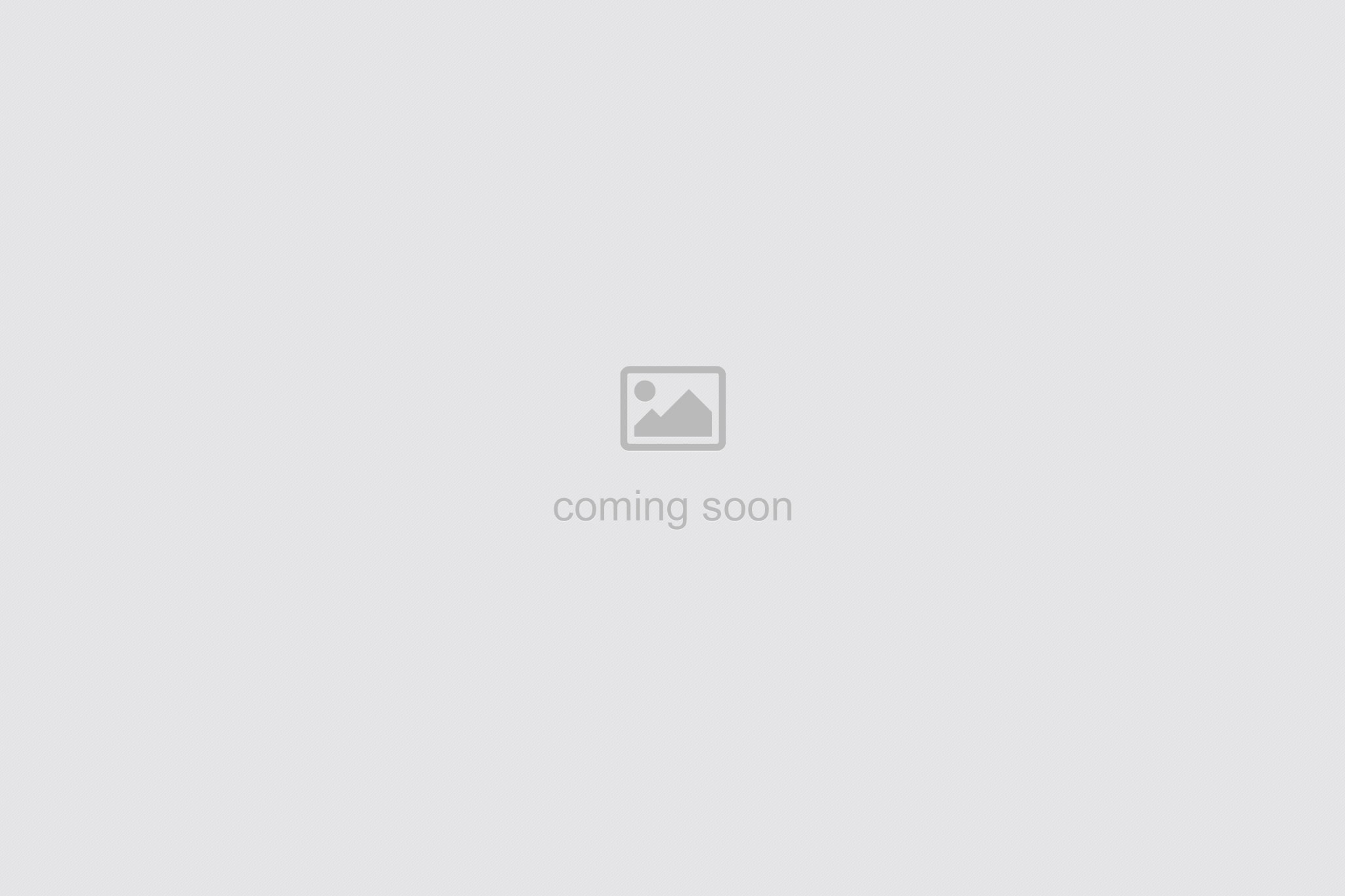プログラムノート(第372回定期演奏会)
2024-05-21
カテゴリ:読み物
チェック
奥田 佳道(音楽評論家)
ショパン(1810~1849)ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21
| 作曲 1829年10月頃~1830年にかけて 初演 1830年3月ワルシャワ、作曲者自身のピアノ |
鍵盤の詩人ショパン若き日の「肖像」を聴く。
美や夢、愛に憧れる楽想が舞い、独特のアクセントをもつ3拍子系の民俗舞曲クヤヴィアク(古都クヤヴィまたはクヤヴィ地方の踊り)のリズムも織り込まれた。第3楽章を彩るクヤヴィアクはマズルカに通じる舞曲で、古き良き時代のポーランドでは結婚式やお祭りに欠かせない輪舞だった。
ノクターンあるいはロマンスを想起させる第2楽章ラルゲットの調べは、ショパンが理想の人と呼んだワルシャワ音楽院の若きソプラノ歌手コンスタンツヤ・グワトコフスカ(1810~1889)を想って書かれたようである。友人ティトゥス・ヴォイチェホフスキへの手紙に、次のような一節がある。
「ひょっとすると僕にとって不幸なことだと思うが、憧れの人を見つけてしまった。まだ一言も話をしていないのだが、この半年もの間、僕は心のなかであの理想の人に忠誠を捧げ、彼女のことを夢見ている。そう想っている間に、僕は協奏曲のアダージョ楽章を書いた。霊感が湧き、(もうひとつ)小さなワルツ#も今朝出来上がった」
#後に作品70-3となるワルツ第13番変ニ長調。
歌姫に恋焦がれたことからも分かるように、そしてモーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の二重唱“お手をどうぞ”による変奏曲変ロ長調作品2を書いたことからも明らかなように、ショパンはオペラ好きだった。フランス・オペラ、そしてベル・カント(美しい声、技)を極めたイタリアのベッリーニ、ロッシーニ作品に関心を寄せ、自身の鍵盤芸術に生かした。
1829年に訪れたベルリン、翌年にはウィーンでもオペラを鑑賞。ウィーン、ケルントナートーア劇場での自作自演コンサートでは、当時流行っていたボイエルデューの歌劇「白衣の婦人」(1825年パリ初演)のアリアに基づく即興演奏も披露している。
いっぽう、ワルシャワ音楽院の恩師ユゼフ・エルスネル(ヨーゼフ・エルスナー 1769~1854)の意向もあり、早くからピアノの管弦楽のための作品づくりを認められていたショパンには、構えの大きなピアノ協奏曲を作曲し、国外での演奏活動を軌道に乗せたいとの野心も芽生えていた。古典的な様式、楽章構成、華やかな技巧性をあわせもつピアノ協奏曲が1830年前後、人気を博していたからである。
当代随一のピアノの名手で、シューベルトもソナタを献呈したかったオーストリアの巨匠フンメルによるロマンティックなピアノ協奏曲第2番、同第3番、そのフンメルのライバルでもあったドイツ人作曲家カルクブレンナーのピアノ協奏曲第1番といった「先例」が、20歳前のショパンを動かす。ノクターンを創始したアイルランドの作曲家ジョン・フィールド(1782~1837)の調べ、協奏的な作品もショパンを刺激したようである。
長年の慣習に鑑みピアノ協奏曲「第2番」と記しているが、完成も初演もピアノ協奏曲「第1番」よりも先だ。ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番、第2番の状況と似ている。
2曲ともショパン20歳の年に初演されたが、二番目に書かれ、1830年10月に初演されたホ短調の協奏曲が1833年に出版されたので第1番。先に完成し1830年3月に初演、1836年に出版されたヘ短調 の協奏曲が第2番となった。
近年新たに編纂された楽譜=ヤン・エキエル教授(1913~2014)編纂のナショナル・エディション(ポーランド音楽出版)では、作曲順とは異なるこの第何番というナンバリングをやめて、シンプルにピアノ協奏曲ホ短調、ピアノ協奏曲ヘ短調と表記。また、作曲者自身がどこまで関与したか、時折話題となる管弦楽パートに関しても、ショパンの意図を“推察・復元”した「コンサート・ヴァージョン」と、従来譜を校訂した「ヒストリカル・ヴァージョン」を制作した。
デッカ・クラシックスからエチュード全集がリリースされたばかりのイム・ユンチャン、この春二十歳になった。ソヒエフ指揮ボストン交響楽団、マケラ指揮パリ管弦楽団とのラフマニノフでも喝采を博した俊英、さあ登場だ。
第1楽章 マエストーソ
第2楽章 ラルゲット
第3楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ
ブルックナー(1824~1896)交響曲第9番 ニ短調 WAB.109〈原典版〉
| 作曲 1887年~1894年 レーヴェ稿初演 1903年2月ウィーン楽友協会、 フェルディナント・レーヴェ指揮ウィーン演奏協会管弦楽団(現在のウィーン交響楽団) 原典稿初演 1932年4月ミュンヘン、 ジークムント・フォン・ハウゼッガー指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 出版 1903年(レーヴェ版) 1934年(原典版、アルフレート・オーレル版) 1951年(原典版、レオポルト・ノヴァーク版) |
祈りの情趣、荘厳、壮麗な調べがホールを満たす。万物創造の瞬間に立ち会うかのような神秘性、摩訶不思議な浮遊感もキーワードとなる。いやそればかりでなく、大胆この上ない音の跳躍に、転調、誤解を恐れずに申せば「きしむ」音響も身上だ。
ベートーヴェンの第9冒頭やワーグナーの「さまよえるオランダ人」序曲を彩る、ドミソで言えばミのない空虚5度の響き。「トリスタンとイゾルデ」の世界に通じる半音階的な進行も添えられた。
今年生誕200年。オーストリアの孤高のシンフォニスト、アントン・ブルックナーが紡いだ最後の交響曲第9番を聴く。
敬虔なカトリック教徒にして大聖堂やコンサートホールでのオルガン演奏の匠だったブルックナーにとって、五線譜に♭記号ひとつの二短調(d-moll、d-minor)は、神=Deusを賛美する調性、神に抱かれ、ひざまずく調性でもあった。
オルガン演奏とりわけ即興の名手だったオーストリアの楽長ブルックナーが、交響曲の世界に目覚めるのは40歳台になってからである。このジャンルの創作に関する限り、大器晩成を地で行く人だった。
生まれ故郷に近いドナウ河畔の古都リンツを離れ、ハプスブルクの帝都ウィーンに移り住んだブルックナーは、ウィーン楽友協会附属音楽院、現在のウィーン音楽演劇大学の対位法(理論)の教授に迎えられた後、オルガンの演奏法や対位法の美学を生かした長篇交響曲を書き始める。
しかしブルックナーが書き始めた交響曲は、当時の交響曲の様式や概念を超越していたために、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団や同フィルゆかりの指揮者、教え子、ウィーン楽友協会の要人を戸惑わすことも多かった。あからさまな拒絶反応も起きた。
それで作曲者は改訂という名の旅に出る。指揮者や弟子筋による愛ゆえの助言、改ざんや短縮演奏もあった。その経緯は実に様々である。
奇蹟な高みに達した交響曲第9番の第1楽章から第3楽章までは、1887年8月から1894年11月末にかけて書かれた。その間、ブルックナーは例によって旧作交響曲の改訂に勤しんでいる。
1896年10月11日日曜午後、ブルックナー、ウィーンの自室で亡くなる。その日の午前中まで交響曲第9番のことを気にかけ、五線紙を手元に置いていた。
別項データのように初演は1903年2月。ブルックナーが召されて7年後の事である。ブルックナーの「良き理解者」だったフェルディナント・レーヴェ指揮、現在のウィーン交響楽団によって行われた。レーヴェによる改ざん、オーケストレーション(管弦楽法)の変更、加筆、削除を伴った、いわゆる「レーヴェ稿」による演奏だった。同年、楽譜つまりレーヴェ版も刊行された。
原典稿での初演は1932年4月、ジークムント・フォン・ハウゼッガー指揮ミュンヘン・フィルによって行なわれた。そのコンサートでは、交響曲第9番受容史を浮き彫りにすべく、レーヴェ版も演奏された。
その後、原典稿を底本とするアルフレート・オーレル校訂版(1934年刊行)、オーレル版に基づくレオポルド・ノヴァーク校訂版(1951年刊行)、ややあってベンヤミン=グンナー・コールス校訂版(2000年、2005年刊行)が出た。
第1楽章から第3楽章の主題、動機、そして遺されたスケッチを用い、第4楽章まで「完成」させる試みも多い。楽譜もいくつか出ている。
ブルックナー芸術の使徒、泰斗(たいと)でもある我らが高関健の考えは次の通り。
「第3楽章まで演奏する。第4楽章については、たとえばマーラーの交響曲第10番と異なり、あまりにも出来上がった部分が少なく、そこから再構成したとしても、音楽的に第1楽章から第3楽章までの水準に遠く及ばない。第4楽章の演奏を考えたことはない」
「1934年刊行のオーレル版に基づいて演奏する。ただしオーレル版はパート譜の製版が最善でなく読みづらいので、オーレル版に残る明らかな誤植だけを訂正し、製版し直したノヴァーク版を使用する。両版の違いはほとんどない。さらに自筆原稿を参照して、作曲者の書き間違えと推定できる点は変更する。」
「コールス版は、自筆原稿に対するさまざまな意見が述べられ、それは理解するが、演奏に関する自分の解釈を楽譜本体に掲載している。その点が原典版の趣旨から離れていると感じられ、私は評価しない。」
楽譜上の楽器編成は木管楽器各3、ホルン8(そのうち4人はワーグナー・テューバ持ち替え)、トランペット、トロンボーン各3、テューバ、ティンパニ、弦楽。なおワーグナーが「ニーベルングの指環」四部作で採用したワーグナー・テューバは通称で、当人およびブルックナーは、単に「テューベン」(テューバの複数形)と記している。ホルンとワーグナー・テューバが第3楽章で奏でる聖歌風の動機をブルックナーは「生からの別れ」と呼んだ。
創造の喜びを、響きの余韻をステージと客席で分かち合いたいものである。
第1楽章 荘厳に、神秘的に
第2楽章 スケルツォ 動きをもって、快活に
ベートーヴェンの第9冒頭やワーグナーの「さまよえるオランダ人」序曲を彩る、ドミソで言えばミのない空虚5度の響き。「トリスタンとイゾルデ」の世界に通じる半音階的な進行も添えられた。
今年生誕200年。オーストリアの孤高のシンフォニスト、アントン・ブルックナーが紡いだ最後の交響曲第9番を聴く。
敬虔なカトリック教徒にして大聖堂やコンサートホールでのオルガン演奏の匠だったブルックナーにとって、五線譜に♭記号ひとつの二短調(d-moll、d-minor)は、神=Deusを賛美する調性、神に抱かれ、ひざまずく調性でもあった。
オルガン演奏とりわけ即興の名手だったオーストリアの楽長ブルックナーが、交響曲の世界に目覚めるのは40歳台になってからである。このジャンルの創作に関する限り、大器晩成を地で行く人だった。
生まれ故郷に近いドナウ河畔の古都リンツを離れ、ハプスブルクの帝都ウィーンに移り住んだブルックナーは、ウィーン楽友協会附属音楽院、現在のウィーン音楽演劇大学の対位法(理論)の教授に迎えられた後、オルガンの演奏法や対位法の美学を生かした長篇交響曲を書き始める。
しかしブルックナーが書き始めた交響曲は、当時の交響曲の様式や概念を超越していたために、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団や同フィルゆかりの指揮者、教え子、ウィーン楽友協会の要人を戸惑わすことも多かった。あからさまな拒絶反応も起きた。
それで作曲者は改訂という名の旅に出る。指揮者や弟子筋による愛ゆえの助言、改ざんや短縮演奏もあった。その経緯は実に様々である。
奇蹟な高みに達した交響曲第9番の第1楽章から第3楽章までは、1887年8月から1894年11月末にかけて書かれた。その間、ブルックナーは例によって旧作交響曲の改訂に勤しんでいる。
1896年10月11日日曜午後、ブルックナー、ウィーンの自室で亡くなる。その日の午前中まで交響曲第9番のことを気にかけ、五線紙を手元に置いていた。
別項データのように初演は1903年2月。ブルックナーが召されて7年後の事である。ブルックナーの「良き理解者」だったフェルディナント・レーヴェ指揮、現在のウィーン交響楽団によって行われた。レーヴェによる改ざん、オーケストレーション(管弦楽法)の変更、加筆、削除を伴った、いわゆる「レーヴェ稿」による演奏だった。同年、楽譜つまりレーヴェ版も刊行された。
原典稿での初演は1932年4月、ジークムント・フォン・ハウゼッガー指揮ミュンヘン・フィルによって行なわれた。そのコンサートでは、交響曲第9番受容史を浮き彫りにすべく、レーヴェ版も演奏された。
その後、原典稿を底本とするアルフレート・オーレル校訂版(1934年刊行)、オーレル版に基づくレオポルド・ノヴァーク校訂版(1951年刊行)、ややあってベンヤミン=グンナー・コールス校訂版(2000年、2005年刊行)が出た。
第1楽章から第3楽章の主題、動機、そして遺されたスケッチを用い、第4楽章まで「完成」させる試みも多い。楽譜もいくつか出ている。
ブルックナー芸術の使徒、泰斗(たいと)でもある我らが高関健の考えは次の通り。
「第3楽章まで演奏する。第4楽章については、たとえばマーラーの交響曲第10番と異なり、あまりにも出来上がった部分が少なく、そこから再構成したとしても、音楽的に第1楽章から第3楽章までの水準に遠く及ばない。第4楽章の演奏を考えたことはない」
「1934年刊行のオーレル版に基づいて演奏する。ただしオーレル版はパート譜の製版が最善でなく読みづらいので、オーレル版に残る明らかな誤植だけを訂正し、製版し直したノヴァーク版を使用する。両版の違いはほとんどない。さらに自筆原稿を参照して、作曲者の書き間違えと推定できる点は変更する。」
「コールス版は、自筆原稿に対するさまざまな意見が述べられ、それは理解するが、演奏に関する自分の解釈を楽譜本体に掲載している。その点が原典版の趣旨から離れていると感じられ、私は評価しない。」
楽譜上の楽器編成は木管楽器各3、ホルン8(そのうち4人はワーグナー・テューバ持ち替え)、トランペット、トロンボーン各3、テューバ、ティンパニ、弦楽。なおワーグナーが「ニーベルングの指環」四部作で採用したワーグナー・テューバは通称で、当人およびブルックナーは、単に「テューベン」(テューバの複数形)と記している。ホルンとワーグナー・テューバが第3楽章で奏でる聖歌風の動機をブルックナーは「生からの別れ」と呼んだ。
創造の喜びを、響きの余韻をステージと客席で分かち合いたいものである。
第1楽章 荘厳に、神秘的に
第2楽章 スケルツォ 動きをもって、快活に
トリオ(中間部)速く
第3楽章 アダージョ 穏やかに、荘厳に
第3楽章 アダージョ 穏やかに、荘厳に