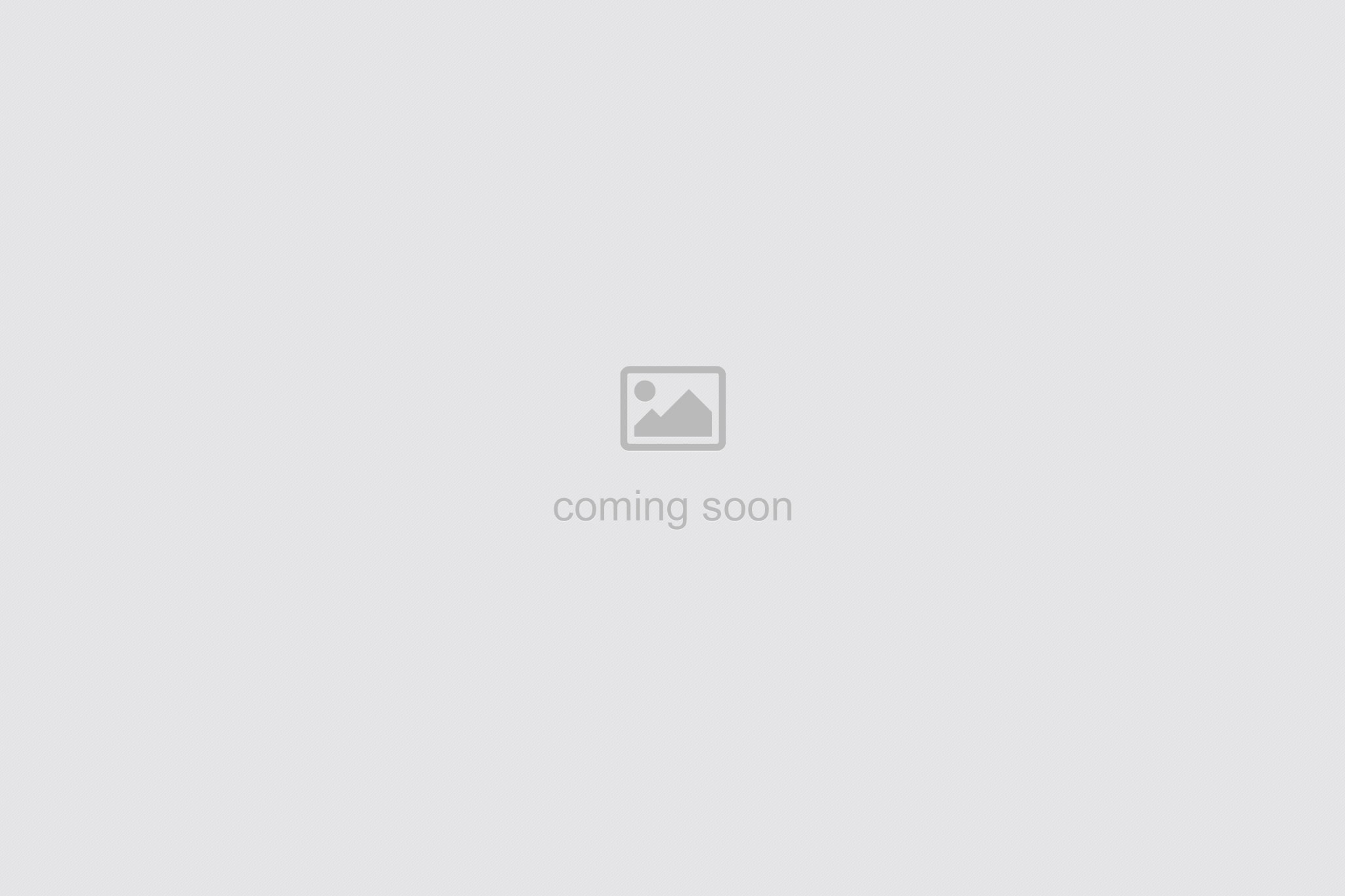プログラムノート(第365回定期演奏会)
2023-07-14
カテゴリ:読み物
チェック
奥田 佳道(音楽評論家)
ラフマニノフ(1873~1943)ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30
| 作曲 1909年9月(完成) 初演 1909年11月28日ニューヨーク、ニューシアター、作曲者自身のピアノ、 ウォルター・ダムロッシュ指揮ニューヨーク交響楽団 (このオーケストラは後にニューヨーク・フィルハーモニックに吸収合併される) |
気宇壮大なロシアン・ロマンに抱かれる。
第1楽章の冒頭、オーケストラの序奏2小節に導かれ、ピアノがユニゾンで聖歌風の調べを紡ぐ。
楽譜にはただp(弱く)と記されている。シンプルだが、これがラフマニノフ、これぞラフマニノフと、早くも心で喝采を叫びたくなる動機。狭い音域を行き来する、このシンプルな調べがピアノ協奏曲第3番の「示導動機」となる。表情やテンポ、音域を変えながら、すべての楽章に顔を出し、烈しくも美しい楽想を有機的に関連づけるのだ。
ラフマニノフは次のように語っている。
「歌い手が歌うように旋律を歌わせたかった」。
鍵盤の巨人セルゲイ・ラフマニノフは、19世紀から20世紀への世紀転換期に創ったピアノ協奏曲第2番ハ短調(1901年の秋に全曲初演)で、作曲家並びにピアノのヴィルトゥオーゾ、華やかな技と音楽性をあわせもつ名手としてさらなる高みに達した。
ちなみに1901年だけで、2台のピアノのための組曲作品17、ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18、尊敬するチェリスト、ブランドゥコフのためにチェロ・ソナタ ニ短調作品19、それに現在作品23の5として愛されている前奏曲ト短調(10の前奏曲の第5番)を書いている。翌1902年には結婚、名ナンバーが並ぶ12の歌曲集作品21も創った。
1904年からボリショイ劇場の指揮者陣に加わり、オペラ指揮者としても2シーズンほど辣腕をふるった後、母国ロシアの政情不安(1905年1月には血の日曜日事件=ロシア第一革命の発端となる出来事も起こった)を避け、ドイツの古都ドレスデンに赴く。ワーグナーの伝統が息づくドレスデンは当時、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)芸術の聖地だった。そのドレスデンで、人気の長篇交響曲第2番ホ短調作品27(1908年サンクト・ペテルブルクで初演)やピアノ・ソナタ第1番ニ短調作品28が完成する。
翌1909年の夏から秋にかけて、ラフマニノフはロシア(タンボフ州イワノフスカ村、モスクワから約500キロ)のサマーハウスで、ピアノ協奏曲第3番の創作に勤しむ。ラフマニノフこのとき36歳。
初のアメリカ演奏旅行で披露する新作が必要だったのだ。勝負曲ゆえ、技巧的で表情豊かなソロは申すに及ばず、第2番以上に凝ったオーケストレーション(管弦楽法)も客席の喜びとなる。オペラや交響詩「死の島」作品29(1909年4月初演)に通じる響きも舞う。
演奏史を。曲は、1909年11月にニューヨークのニューシアターとカーネギーホールで行なわれたウォルター・ダムロッシュ(1862~1950)指揮のニューヨーク交響楽団の定期公演(二日間)で、ラフマニノフ自身のピアノにより初演された。
年明けにもカーネギーホールで演奏された。グスタフ・マーラー(1860~1911)指揮ニューヨーク・フィルハーモニックの定期公演。
この歴史的ステージを彩ったプログラムは、バッハ=マーラー編曲/管弦楽組曲、ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第3番、ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死、スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲だった。
ラフマニノフは、オーケストラに対し根気よく緻密なリハーサルを行なった指揮者マーラーに、半ば呆れ驚きつつ、最終的には敬意を表したようである。ハプスブルクの支配下とはいえボヘミア!出身のユダヤ人マーラーには、スラヴ流儀の音楽への愛および聖歌風の旋律や舞曲・民謡への共感があったのだ。
聴きどころは枚挙にいとまがない。長身で、手もドからオクターヴ上のラまで届いたというラフマニノフは、第1楽章のカデンツァを二種類創った。近年はOssia(または、もしくはの意)と記された「大カデンツァ」を弾く人が多い。壮絶なカデンツァを受け継ぐフルート、オーボエ、クラリネット、ホルンのリレーにも胸ときめく。聴こえてくるのは第1楽章の主題である。
うねりを帯びた音楽が、あたかも螺旋(らせん)を描くかのように昇り詰め、演奏家も聴き手もカタルシスを味わう第3楽章コーダ(終結部)の創り。それに決然とした、歯切れのいいエンディングも、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を聴く醍醐味となる。
今年は生誕150年、没後80年のラフマニノフ・イヤー。デビュー45周年も視野に入ってきた清水和音の十八番を満喫したいものである。
第1楽章 アレグロ・マ・ノン・タント ニ短調
第2楽章 間奏曲、アダージョ 嬰ヘ短調 (実際はニ短調)~変ニ長調~嬰へ短調
アタッカで(切れ目なく)第3楽章へ
第3楽章 フィナーレ、アラ・ブレーヴェ(2分の2拍子) ニ短調~ニ長調
ラフマニノフは次のように語っている。
「歌い手が歌うように旋律を歌わせたかった」。
鍵盤の巨人セルゲイ・ラフマニノフは、19世紀から20世紀への世紀転換期に創ったピアノ協奏曲第2番ハ短調(1901年の秋に全曲初演)で、作曲家並びにピアノのヴィルトゥオーゾ、華やかな技と音楽性をあわせもつ名手としてさらなる高みに達した。
ちなみに1901年だけで、2台のピアノのための組曲作品17、ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18、尊敬するチェリスト、ブランドゥコフのためにチェロ・ソナタ ニ短調作品19、それに現在作品23の5として愛されている前奏曲ト短調(10の前奏曲の第5番)を書いている。翌1902年には結婚、名ナンバーが並ぶ12の歌曲集作品21も創った。
1904年からボリショイ劇場の指揮者陣に加わり、オペラ指揮者としても2シーズンほど辣腕をふるった後、母国ロシアの政情不安(1905年1月には血の日曜日事件=ロシア第一革命の発端となる出来事も起こった)を避け、ドイツの古都ドレスデンに赴く。ワーグナーの伝統が息づくドレスデンは当時、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)芸術の聖地だった。そのドレスデンで、人気の長篇交響曲第2番ホ短調作品27(1908年サンクト・ペテルブルクで初演)やピアノ・ソナタ第1番ニ短調作品28が完成する。
翌1909年の夏から秋にかけて、ラフマニノフはロシア(タンボフ州イワノフスカ村、モスクワから約500キロ)のサマーハウスで、ピアノ協奏曲第3番の創作に勤しむ。ラフマニノフこのとき36歳。
初のアメリカ演奏旅行で披露する新作が必要だったのだ。勝負曲ゆえ、技巧的で表情豊かなソロは申すに及ばず、第2番以上に凝ったオーケストレーション(管弦楽法)も客席の喜びとなる。オペラや交響詩「死の島」作品29(1909年4月初演)に通じる響きも舞う。
演奏史を。曲は、1909年11月にニューヨークのニューシアターとカーネギーホールで行なわれたウォルター・ダムロッシュ(1862~1950)指揮のニューヨーク交響楽団の定期公演(二日間)で、ラフマニノフ自身のピアノにより初演された。
年明けにもカーネギーホールで演奏された。グスタフ・マーラー(1860~1911)指揮ニューヨーク・フィルハーモニックの定期公演。
この歴史的ステージを彩ったプログラムは、バッハ=マーラー編曲/管弦楽組曲、ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第3番、ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死、スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲だった。
ラフマニノフは、オーケストラに対し根気よく緻密なリハーサルを行なった指揮者マーラーに、半ば呆れ驚きつつ、最終的には敬意を表したようである。ハプスブルクの支配下とはいえボヘミア!出身のユダヤ人マーラーには、スラヴ流儀の音楽への愛および聖歌風の旋律や舞曲・民謡への共感があったのだ。
聴きどころは枚挙にいとまがない。長身で、手もドからオクターヴ上のラまで届いたというラフマニノフは、第1楽章のカデンツァを二種類創った。近年はOssia(または、もしくはの意)と記された「大カデンツァ」を弾く人が多い。壮絶なカデンツァを受け継ぐフルート、オーボエ、クラリネット、ホルンのリレーにも胸ときめく。聴こえてくるのは第1楽章の主題である。
うねりを帯びた音楽が、あたかも螺旋(らせん)を描くかのように昇り詰め、演奏家も聴き手もカタルシスを味わう第3楽章コーダ(終結部)の創り。それに決然とした、歯切れのいいエンディングも、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を聴く醍醐味となる。
今年は生誕150年、没後80年のラフマニノフ・イヤー。デビュー45周年も視野に入ってきた清水和音の十八番を満喫したいものである。
第1楽章 アレグロ・マ・ノン・タント ニ短調
第2楽章 間奏曲、アダージョ 嬰ヘ短調 (実際はニ短調)~変ニ長調~嬰へ短調
アタッカで(切れ目なく)第3楽章へ
第3楽章 フィナーレ、アラ・ブレーヴェ(2分の2拍子) ニ短調~ニ長調
チャイコフスキー(1840~1893)交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」
| 作曲 1893年2月~8月 初演 1893年10月サンクト・ペテルブルク、作曲者自身の指揮による帝室ロシア音楽協会の公演で |
19世紀ロシア・オーケストラ芸術の最高峰を聴く。
チャイコフスキーは「悲愴」を書く4年前にこう述べている。
「私は、私の作曲人生全体の終わりを示すような壮大な交響曲を書きたいと考えています」。
「人生」という言葉に想いを寄せていた。しかし「人生交響曲」案を破棄、音楽的な素材はピアノ協奏曲第3番に移植されたが、そのコンチェルトも未完に終わった。
1893年冬、彼には別のアイディアが芽生えていた。
「今度の交響曲はプログラム(標題性)をもっていますが、それが何であるかは謎にしておきましょう。(推測したい人に)推測させればいい。最後の楽章はアレグロではなく、アダージョになります」
曲は1893年の冬から夏にかけて書かれ、8月半ばにオーケストラ浄書譜が完成している。同年10月16日(ユリウス=ロシア暦)/10月28日(西暦)に、サンクト・ペテルブルクの帝室ロシア音楽協会のコンサートで作曲者自身の指揮により初演された。
その9日後(ロシア暦10月25日、西暦11月6日)に、チャイコフスキーはサンクト・ペテルブルクで急逝する。53歳だった。
余談を。「悲愴」の年つまり1893年は音楽史が賑やかである。ニューヨークのカーネギーホールでドヴォルザークの交響曲第9番ホ短調「新世界より」が(12月15/16日に)初演され、イタリアではヴェルディ最後のオペラ「ファルスタッフ」が(2月9日に)ミラノ・スカラ座で初演、プッチーニの出世作「マノン・レスコー」が(2月1日に)トリノ王立歌劇場で初演された年なのだ。
交響曲第6番ロ短調の自筆譜に書かれたキリル文字を欧文表記にすると、Pateticheskaya Simfoniyaパテティーチェスカヤ・シンフォニヤとなる。強い感情、燃えるような情念をもった交響曲という意味だ。
いっぽうチャイコフスキーはフランス語のPathetiqueパテティークという表記も出版社とのやりとりなどで普通に使っている。曲は最愛の甥ウラディーミル・ダヴィドフへの献辞をもつ。
交響曲のあり方を問い直すかのような「悲愴」、とくに最終楽章のあり方が、シベリウス、マーラー、ショスタコーヴィチの一部交響曲に与えた影響は計り知れない。弦楽による「浄化」もキーワードになりそうなマーラーの交響曲第3番、第9番の各最終楽章を挙げるまでもない。
円光寺雅彦と仙台フィルハーモニー管弦楽団は1989年5月27日、サントリーホールでの東京特別演奏会で「悲愴」を奏でた。同年1月31日に63歳で召された芥川也寸志(仙台フィル音楽総監督)に捧げる公演だった。この「悲愴」はCD化されている。
第1楽章:アダージョ ロ短調
ため息の動機や愛を感じさせる響き、うねりを帯びた烈しい情趣に彩られた楽章。2度音程の下行、4度下行の動機が鍵を握る。
チャイコフスキーは、英パーセル(1659~1695)のオペラ「ディドーとエアネス」の“ディドーのラメント”(哀歌、私が地中に横たえられた時)、そしてベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番ハ短調作品13「悲愴」を、さて意識したのだろうか。
ロシア正教会の死者のための歌<主よ、汝の眠りし私たちの魂を、聖人とともに安んぜしめ給え>の調べが織り込まれている。この調べは、神と教会の楽器だったトロンボーンに委ねられた。
チャイコフスキーが記した最弱音の指示は何とppppppである。
第2楽章:アレグロ・コン・グラツィア(優美さをもったアレグロ) ニ長調
4分の5拍子(2拍子プラス3拍子)で書かれた摩訶不思議なワルツ。楽章のほどでは心の鼓動も聴こえる。
チャイコフスキーはピアノのための「18の小品」作品72の第16曲で、ずばり<5拍子のワルツ>と題した音楽を書いた。ロシア民謡や東欧スラヴ系の民俗音楽では、いつもではないものの、“3拍子ではないワルツ”を聴くことが出来る。ロシア語の語感や音節との関連を指摘する文献もあり、興味は尽きない。そういえば、ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」のプロムナードも5拍子、6拍子、7拍子だ。
第3楽章:アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ ト長調
スケルツォとマーチの要素を兼ね備えた劇的な楽章。
第4楽章:アダージョ・ラメントーソ(嘆きのアダージョ) ロ短調
冒頭の悲嘆的な調べは、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの精妙な絡み合いによって創られている。演奏によっては虚無的に響くこともあるタムタム(ゴング=銅鑼)の一打を契機に、音楽は哀しみにくれてゆく。コントラバスのピッツィカートは最後、末期(まつご)の鼓動なのか。
ムソルグスキー、チャイコフスキー、ラフマニノフ、プロコフィエフ、ハチャトゥリアン、ショスタコーヴィチの音楽が示すように、ロシアおよびロシア系の作曲家と「鐘の音」は相思相愛である。古き良き時代のロシアでは、悦ばしいときも哀しいときも鐘(kolokol/zvuk kolokola)なのだ。ロシアには鐘の文化史という研究領域もある。
響きの余韻をステージと客席で分かち合いたいものである。