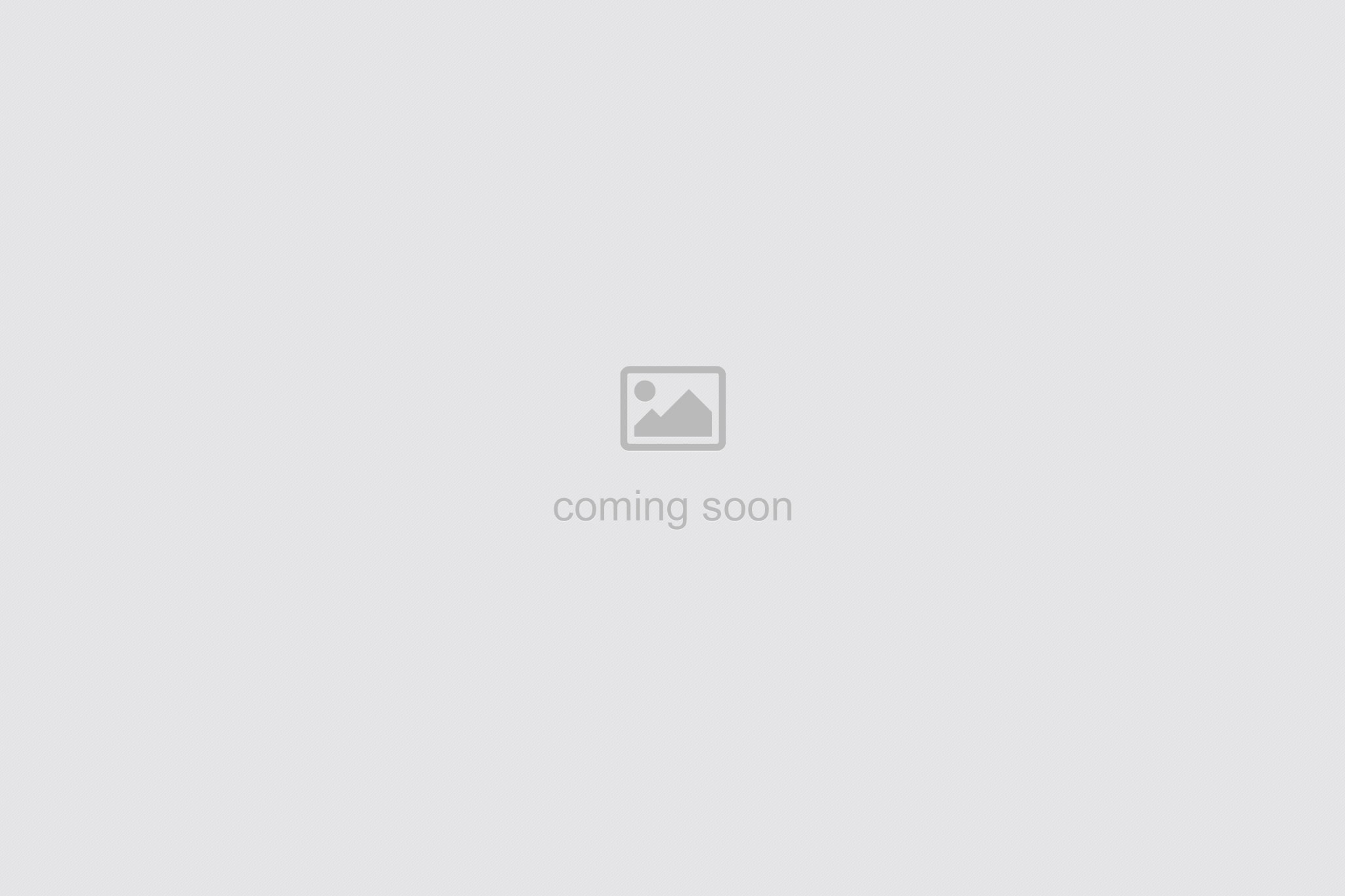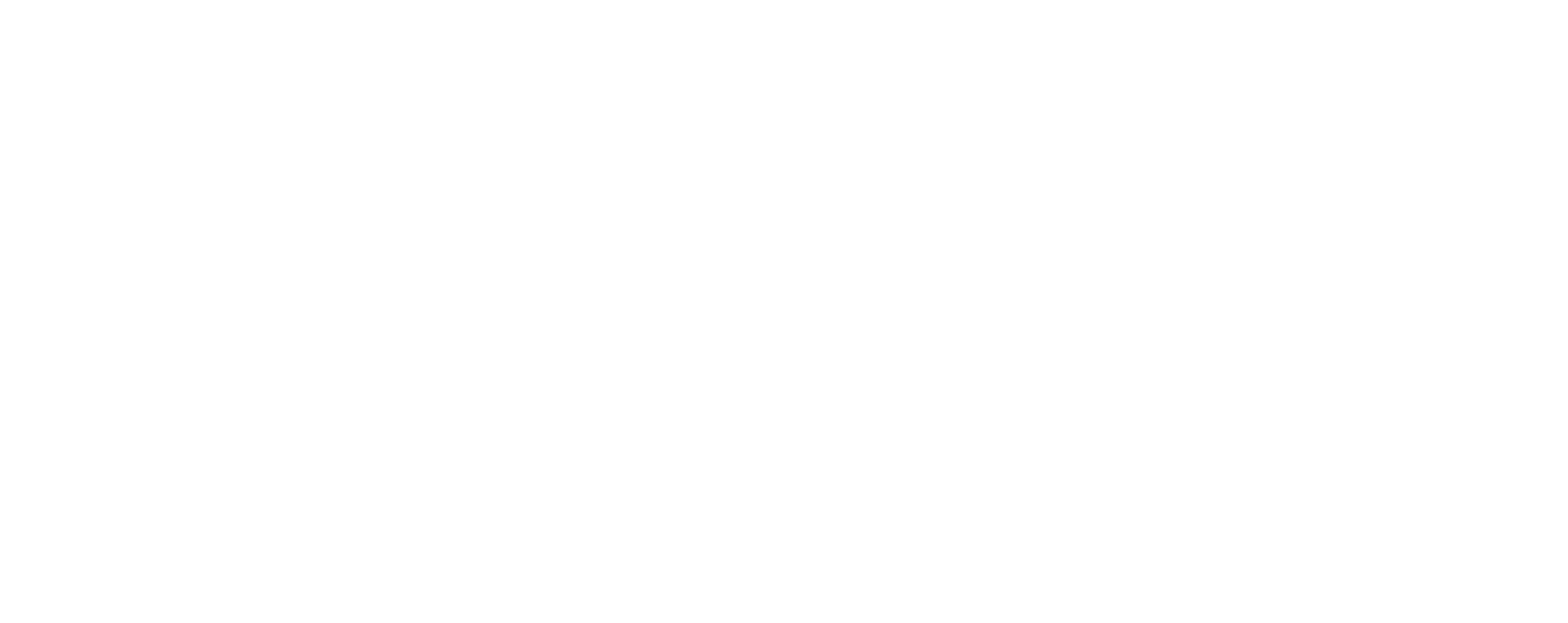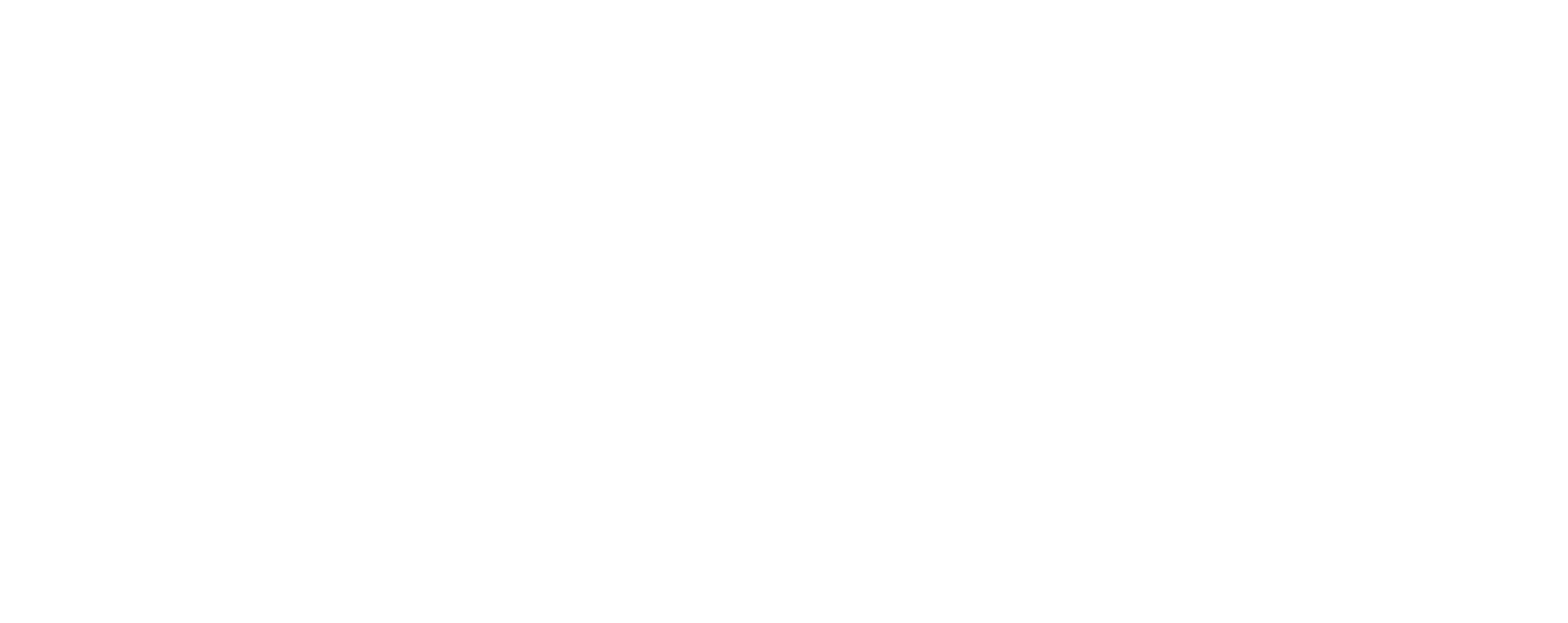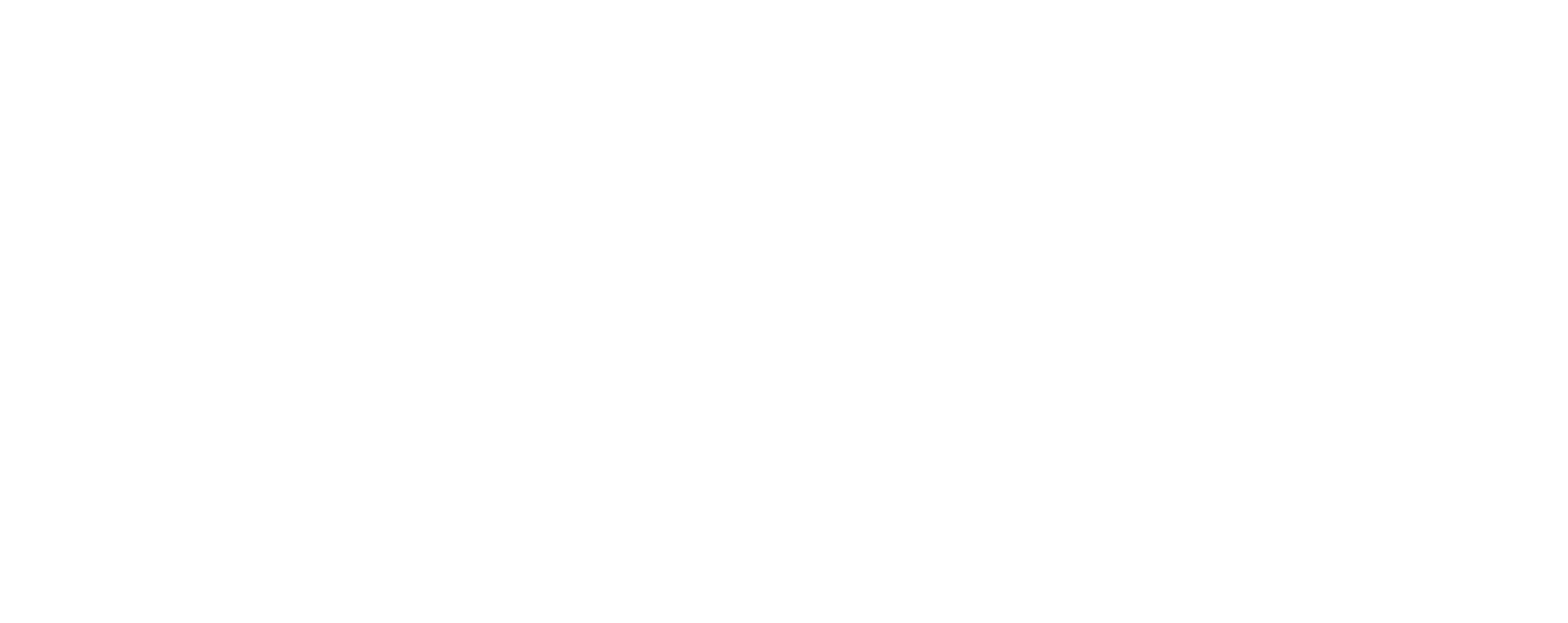プログラムノート(第361回定期演奏会)
2023-02-14
カテゴリ:読み物
チェック
奥田 佳道(音楽評論家)
ベートーヴェン(1770~1827)ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73「皇帝」
| 作 曲 1808年~1810年 初 演 1811年1月ウィーン、ロプコヴィツ侯爵邸、ルドルフ大公のソロ 公開初演 1811年11月ライプツィヒ、ゲヴァントハウス管弦楽団の1811年/1812年シーズン 第7回定期演奏会(指揮者不詳)、ヨハン・フリードリヒ・シュナイダーのソロ |
壮麗極まりない曲の開始部はいつだって関心の的。この上なく劇的だ。
まさに「皇帝」Emperorの趣。風格がある。しかしこのニックネームにベートーヴェンは関与していない。「皇帝」という愛称は、ロンドンで活躍したドイツ人ピアニストで楽譜出版業でも成功したヨハン・バプティスト・クラーマー(1751~1858)が考案したと考えられている。そしてベートーヴェンが亡くなった後にロンドンで広まった。
ゆえにドイツ語のKaiserカイザー=皇帝ではなく、エンペラーなのだ。命名に関与した可能性が高いクラーマーといえば、ピアノ学習者がお世話になる「クラーマー=ビューロー 60の練習曲」でも名高い。
ピアノ協奏曲第5番は1808年暮れから1810年初めにかけて、ベートーヴェンが38、9歳の時に創られた。強じんな芸術的意志と覇気、来たるロマン派時代を映し出す大胆かつ芳醇な楽想が身上だ。
ソリストが即興を披露する場だった「カデンツァ」部を、あたかも口上のごとく、曲の最初のところに持ってきた上に、自由な演奏は認めないとばかりに、そのフレーズを楽譜にすべて書き込んだ。自分(作曲者)以外の演奏者を見据えた措置だろう。しかもその「カデンツァ」部は和音を分散するアルペッジョ、トリル、音階を駆使した壮大なものである。
五線譜に♭記号3つの変ホ長調から、理論的にはとても遠い#記号5つのロ長調へ。高貴な歌謡旋律が舞う第2楽章に抱かれる。
その第2楽章と動的な第3楽章を繋ぐフェルマータの効果も絶大だ。
ファゴットとホルンの半音下降と持続音に導かれ、独奏ピアノがフィナーレ楽章の主題を告げる、あの場面。そして喜ばしいロンド楽想がアレグロで駆け出す。第3楽章ロンドの「幕切れ」を導くティンパニとピアノの対話も心憎い。
第4番(1808年暮れにアン・デア・ウィーン劇場で公開初演)までのピアノ協奏曲はベートーヴェン自身のソロで初演されたが、第5番は事情が異なる。ベートーヴェンは1814年春までピアノを弾いたのだが…。
このコンチェルトは1811年1月、ウィーンのロプコヴィツ侯爵邸でルドルフ大公(1788~1831)のピアノによって私的に弾かれた。ルドルフ大公はベートーヴェン芸術の理解者、支援を惜しまないパトロンにしてピアノ、作曲の弟子。大公は、ベートーヴェンからピアノ協奏曲第4番ト長調、第5番変ホ長調「皇帝」、ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調「告別」、ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調「大公」、ピアノ・ソナタ第32番ハ短調、それに「ミサ・ソレムニス」ニ長調を献呈されている。作曲家としても「ロッシーニの主題による変奏曲」やクラリネット三重奏曲などを遺した。
ちなみにルドルフ大公は神聖ローマ帝国レオポルト2世の末の息子である。女帝マリア・テレジア直系の血筋を持ちながらも健康面に不安があったことも手伝い、政治権力の中枢から離れ、芸術、宗教の世界に生きた人だった。早すぎる晩年にはオルミュッツ(現在のチェコ、モラヴィア地方オロモウツ)の大司教に就任している。
ルドルフ大公によって私的に弾かれた「皇帝」の公開初演は同年11月、ライプツィヒのゲヴァントハウス会館。ソロはかの地の鍵盤の名手ヨハン・フリードリヒ・シュナイダー(1786~1853)に委ねられ、かの地の「総合音楽新聞」に絶賛評が掲載されている。
なおその日はハイドンの交響曲ニ長調(不詳)で始まり、イタリアの作曲家モラッキのオペラのナンバー、ピアノフォルテ協奏曲と書かれた当作品、当時現役のドイツの作曲家ペーター・ヴィンターの序曲、それに「フィガロの結婚」の終景が演奏された。これが当時の一般的なオーケストラ公演だった。
翌1812年4月には、ベートーヴェンの愛弟子にして日本では教則本の著者としても名高いカール・チェルニー(1791~1857)がウィーンで弾く。これがウィーンでの公開初演。ややあって1829年には20歳のメンデルスゾーンがロンドンで初披露。フランツ・リスト、クララ・シューマン、フェルッチョ・ブゾーニも好んで弾いた。ブゾーニとマーラーが共演した1899年3月のウィーン・フィル定期公演も音楽史に燦然と輝く。
小山実稚恵の十八番でもある。サントリーホールで「以心伝心」と題した新たなConcerto企画をスタートさせた彼女は、今年10月の第2回公演で「皇帝」を弾く。
第1楽章:アレグロ 変ホ長調 4分の4拍子
第2楽章:アダージョ・ウン・ポコ・モート ロ長調 2分の2拍子(ヘンレ版)
第3楽章:ロンド、アレグロ・マ・ノン・トロッポ 変ホ長調 8分の6拍子(ヘンレ版)
ショスタコーヴィチ(1906~1975)交響曲第10番 ホ短調 作品93
| 作 曲 1953年 初 演 1953年12月レニングラード(現サンクト・ペテルブルク)、 エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 日本初演 1954年11月日比谷公会堂、上田仁(うえだ・まさし)指揮 東京交響楽団 |
20世紀半ばの1953年にソヴィエト連邦(1922年から1991年まで存在した社会主義国家)で書かれた長篇交響曲を聴く。
同年暮れに初演された交響曲第10番は、ソヴィエト連邦の最高指導者/初代閣僚会議議長ヨシフ・スターリン(1878~1953)が亡くなって最初に書かれたシンフォニーである。なおスターリンは1953年3月5日、74歳で死去した。奇しくもその日プロコフィエフ(1891~1953)も亡くなっている。
1945年11月に、エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団により初演された交響曲第9番が──戦勝を祝う記念碑的大作ではなく、機知に富んだ軽妙洒脱な作品だったがゆえに──1948年のいわゆるジダーノフ批判(芸術文化への厳しい管理体制)に巻き込まれたショスタコーヴィチにとって、第10番は実に8年ぶりの交響曲だった。いっぽう「優れた作曲家が交響曲を書かない」ことを問題視した<ソヴィエト音楽>誌編集長の論説に応えての創作でもあった。
初演は成功したものの、ソヴィエトではイデオロギー(思想)と音楽技法の両面から「異議」が発せられ、作曲家同盟の批評部会が主導する形で、いわゆる<第10論争>が巻き起こる。1954年春には作曲家同盟主催のシンポジウムも開催され、その冒頭でショスタコーヴィチは「私はこの交響曲で人間の思想と情熱を描きたかった」と公式に発言。結果、様々な思惑が絡んだ<第10論争>は終結へと向かう。もちろん曲を傑作と認めて、である。
実はショスタコーヴィチ、この曲を書いている頃、エリミーラ・ナジーロヴァ(1928~2014)という元教え子のピアニスト/作曲家と親しく手紙を交わしていた。書簡集が明らかになったのは先のシンポジウムから40年後のこと。そのなかで交響曲第10番の第3楽章に現れる5音動機について説明、自ら分析も行なっていたのである。
こうした創作の「背景」は、ロシア音楽に造詣の深い音楽学者で国際音楽学会ショスタコーヴィチ・セクション アジア代表委員でもある一柳富美子(ひとつやなぎ・ふみこ)氏の尽力によって日本に伝えられた。
第1楽章 モデラート ホ短調 4分の3拍子
気宇壮大な交響曲の幕開け。楽想の連携も意表をつく展開も素晴らしく、古典派交響曲ひとつ分の演奏時間を要する。
弦による荘重な序奏(E-Fis-G ミ・ファ#・ソの3音を基音とする)に導かれ、クラリネットが第1主題を紡ぐ。劇的に発展した後、フルートと弦のピッツィカートが摩訶不思議なワルツの始まりを告げる。ショスタコーヴィチお得意のワルツと言いたいが、あくまでワルツふうだ。
ちなみに冒頭の序奏は交響曲第10番の「示導動機」のひとつで、ここぞという場面を彩る。この動機、リストの「ファウスト交響曲」との近似性も指摘される。
第2楽章 アレグロ 変ロ短調 4分の2拍子
これぞ才人ショスタコーヴィチのスケルツォ。精妙に書かれた管弦の各パートが、何かに駆り立てられるかのように、疾走する。いつもながら鮮烈、効果的に響く打楽器たち。ムソルグスキーの歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」や「禿山の一夜」ふうの響きも、ほのめかされる。あっという間に終わる。
第3楽章 アレグレット ハ短調 4分の3拍子
エピソード風に登場する動機はD-Es-C-H音(独語発音デー・エス・ツェー・ハー)=レ・ミ♭・ド・シで、これがDimitri Schostakowitsch(独語)自身。4音を大文字で記せばD.SCHostakowitschとなる。ショスタコーヴィチお得意の音による署名、音名象徴だ。
その4音と呼応するのがホルンによるE-A-E-D-A音=ミ・ラ・ミ・レ・ラで、これが書簡を交わしていた女性Elmira Nazirovaエリミーラ・ナジーロヴァを表わす。Elmiraのlとrに母音aを加えるとE-lA-E-D-rAとなる。
この動機は、マーラーの交響曲「大地の歌」の冒頭主題から導き出されたようである。ショスタコーヴィチ自身の解説によれば、不吉な運命の象徴だ。
想いを寄せていた(と思われる)エリミーラの「名前」をホルンで都合12回も呼びながら、あの4音は死や別れを意味するとは? ショスタコーヴィチの本心は、例によってと言うべきか、誰にも分からない。
第4楽章 アンダンテ~アレグロ ロ短調~ホ長調 8分の6拍子~4分の2拍子
管弦楽法の匠ショスタコーヴィチの筆致が冴え渡ったフィナーレで、弦楽と木管のソロを効果的に交えた叙情楽想から、アレグロ部ヘの転換がまた鮮やかだ。
自作や諸先輩作曲家からの、ほのめかしも添えられた。ソロ、パートの聴きどころは枚挙にいとまがない。シリアスな響きもユーモアも秘密のメッセージもお任せあれ、と言いたげな作曲家がここにいる。そして音による署名D-Es-C-H音が壮絶に響く。
仙台フィルの次期常任指揮者高関健は、ショスタコーヴィチ芸術の泰斗(たいと)でもある。